はじめに
この数年COVID‑19の流行によって、長らく歓声が失われていた音楽ライブであったが、そんな人々を悩ませた感染症との付き合いもひとまず一旦の区切りを迎えたと言ってもいいのだろうか、最近では発声が解禁されることも増えてきた。私がぽつりぽつりと参加したイベントでも久々に観客たちの声を聞くことがあり、人々が歓声を上げる様子からは今までの鬱憤を晴らすかのように感じられた。声出しが許可されるようになってしばらくというもの、演者も半ばお決まりのように「皆の声が聞こえて、レスポンスが感じられて嬉しい」というようなことを口にしているのを聞いていた。
抑圧からの解放、こうした実感というのは、恐らくシーンに携わる人々にいくらか共有されている感覚なのではないだろうか。
私は単なるいちファンなのだが、それでもここ数年の音楽業界の逆境をものすごく肌で感じていた。音楽を楽しむということ、特にクラブやライブで人々が集まっての催しというのは、しばらく色々な苦難と共にあったように感じられた。感染症の流行という危機は、人々が狭い空間に密集することをよしとしなかったのである。
そんな中でも配信イベントに無声イベントと、様々な方法で音楽シーンは継続してはきたものの、それでも潰れたクラブやライブハウスの話も何度も残念ながら耳にした。人が集まることがダイレクトに感染に繋がってしまうこともそうだが、特に日本全体に危機的な雰囲気が充満していた頃には、生活もままならないのに遊んでいる場合ではない、と判断した人々もいたのだろうと思う。ちょっとした非日常を提供する音楽は、故に日常そのものが揺らいだ時に、真っ先に人々の生活から切り離されてしまうというのも仕方のないことなのかもしれない。
ところで、こうした有事における音楽の立ち位置について、私はふと思い出すことがある。それは2011年の東日本大震災の際に、数々のイベントが自粛めいた当時の流れで中止になったことだ。開催するにしても、電力逼迫の情勢を受け、電気アンプを使わないアンプラグドのライブで節電のポーズが取られることも珍しくはなかった。どこで聞いたか忘れたが、「アンプよりも毎日使うドライヤーのほうがよほど電気を使うだろうに」などと誰かが愚痴っていたような気がする。
ともかく、2011年のときも、2020年のときも、日常がとてつもなく暗い空気のヴェールに覆われた時に、音楽というのはいつも――極端な言い方をしてしまえば――「無駄」なものとして扱われてしまう悲しさがあった。とはいえ、真っ先に解決しなければならない問題に抗わなければならないような瞬間に、音楽ということの優先順位がどうしたって下がってしまうというのは、仕方のないことでもあるのだろう。
この震災のときに多くの有名ミュージシャンがメッセージを歌に乗せて、「被災地への支援の呼びかけ」だとか、あるいはもっとシンプルに「頑張ろう」だったりということを呼びかけたりしていた。このとき、誰も彼もが枕詞に「何もできないけれど、せめて」などとつけながら音楽を放っていた印象がある。偉そうなことが言える立場では全く無いのだが、私にとってはこのような危機的状況において――これは当たり前のことでもあるのだが――音楽はなんて無力なんだ、と同時に思う時期でもあった。
それでも私は音楽の持つ力を疑ったことはない。それはみんなの心を動かすだとか一つにするだとか、そんな大きなことではなくて、極めて個人的な実感としてだ。必死にやりくりする日常の中で、どれだけ音楽という「無駄」に心を癒やされたことか。今とて、まだ何もかもが片付いたとはとても言えないが、それでもなんとかかんとか日常への回帰を感じる中で、人々がライブ会場で弾けるように声を出している。
そのことに、私は音楽の持つ、癒しの力とでも言うべきものを感じるのだ。
『Lapis Re:LiGHTs』における音楽
※本記事では「Lapis Re:LiGHTs」をアニメ作品、「ラピスリライツ」をコンテンツ全体の呼称として使い分けることとする。
さて、この「音楽の持つ力」とでも言うべきことについて、今述べたような価値観に立脚しているのではないか、と私が考えているアニメ作品がある。2020年放送のテレビアニメ『Lapis Re:LiGHTs』である。これは魔法×アイドルをテーマにした一連のコンテンツのメディアミックスの一環で生まれたアニメ作品であった。
![START the MAGIC HOUR[通常盤][CD] START the MAGIC HOUR[通常盤][CD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61rK97T7lPL._SL500_.jpg)
アルバム『START the MAGIC HOUR』
このアニメはアイドル(音楽)作品として見たときにやや奇異な作品となっている。というのも、物語において音楽が軸となっているのかわかりにくい、という作りになっているからだ。物語の主人公ティアラは一人前の魔法使いになるために学園に入学し、魔法の勉強に取り組んでいくのだが、ここで音楽というのははじめそれほど重要な要素としては登場しない。
例えば、3話では丸々バンプボール*1の試合を通じて魔法の扱い方の技巧の差やティアラたちの成長を描写している。作品にとって音楽がメインであれば、こうした部分こそ音楽を用いるほうがスマートであるように思われるにもかかわらず、である。

『Lapis Re:LiGHTs』という作品のシナリオは、特に音楽アニメとして見た場合、どういう意図で組み立てられているのか一見するとわかりにくかったように感じる。そもそも、ティアラの「立派な魔女になる」という目標に対して音楽というアプローチは必ずしも必要ではなく、彼女を含めた班メンバーは先に挙げた球技の試合だとか、あるいは古びた洋館での幽霊退治だとか、そういう方向で評価を得ようとしている。音楽要素といえば、毎話各グループのオルケストラというライブパートが定期的に入るぐらいだが、これは特別物語上の必然性はないように感じられ、このノルマ的な構成によって本作はギリギリ音楽モノとしての姿を保っている……という奇妙な作りであるように思われた。
ちなみに、ラピスリライツというのはメディアミックスコンテンツであり、他の媒体だと全く違うストーリー展開だったりする。ノベルやコミックでは、ティアラたちはシンプルにオルケストラでの成功を最初から目指すという、素直なアイドルストーリーが描かれていた。そう考えると、やはりこのアニメの作りというのはなかなか独特である。
しかし、こうしたアニメの序盤〜中盤の作りは、ティアラがオルケストラ(音楽)という存在にたどり着くまでに時間をかけているから、と見るとスッと腑に落ちる。まず、王宮から身一つで飛び出してきたティアラは学園や魔法のみならず、世の中のことを全く知らないのだ。
ちなみに、このティアラが知る/知らないというのは本作において極めて重要な要素で、頭から尾まで本作を丸々貫く屋台骨と言っても過言ではないと思う。パンプボールにしろ、ティアラ(たち)はルールの無知という原因*2で敗北している。
1話でティアラが学園を訪れて校内を見て回ることや、4話で部活動の見学をすること。そして、2話を始めとして「オルケストラ」にふれることで、音楽の持つ力を知っていき、そして自分たちも挑戦しようという決心に至ること。『Lapis Re:LiGHTs』の物語は、とにかくティアラが新たな知識や知見を得ていくことで進んでいくのだ。

そして、このアニメを見る視聴者の目線というのもティアラと重ねられていて、彼女が経験していくことによって、学園や世界のあり方というものがだんだんと見ている側にもわかるようになっている。
終盤になると、今まで一見意図が見えなかったオルケストラのシーンも、作中世界でどういう役割があるのか、ということもわかってくる。オルケストラというのが住民の魔力を結集させるシステムというのは7話でLiGHTsがオルケストラに挑戦をするあたりでわかるのだが、更にこれは実は学園の存在する都市マームケステルを魔獣から防ぐ、結界防衛システムでもあることが終盤の11話で判明する。
恐らく、このあたりはオルケストラ(音楽)が物語の展開に作用するための設定なのだろう。
ともかくここで私が注目したいのは、この音楽(オルケストラ)の持つ重大な設定がアニメを見ていく上では終盤まで秘匿されている、という本作の構造だ。つまり「一見気が付かなかったけれど音楽というのは人々の生活を支えているのだ!」というのが、アニメ『Lapis Re:LiGHTs』の構成なのである。すなわち、ここには「音楽というのは一見役に立たない」という価値感が横たわっているのである。
最後の最後でようやくティアラが姉・エリザの歌によって救われていたことが判明するのも、一貫した音楽の力(そしてその、さりげなさ)の描き方であると思う。

実用的な魔法と、そうでない音楽
『Lapis Re:LiGHTs』のオルケストラというのは、魔法によって演出されている。それは文字を浮かべたり、ライトを使った演出であったりするわけなのだが、こうした魔法の娯楽的な活用というのは、実はこのアニメにおいてそれほど描写されてはおらず、どちらかといえば実用的である描写が多い。
中盤の5,6話でテントを広げ、着火し、明かりをつけ……という、キャンプにおける様々な妙に細かい魔法描写が見られるのは本作の意外な面白さの一つであるが、ここでの魔法は間違えなく実用的なものである。他にも、10話の王宮に侵入する際にも、空中移動に透明化に鉄格子の破壊、更には護衛の兵士との戦闘に……と魔法は縦横無尽にその実用性を見せている。

そもそも、学園で教えている魔法というものは、矢を爆発させたりナイフを増やしてみたりと、戦闘用の技術が多分に含まれている。これを踏まえると、3話にて何故かドッジボールのような球技を採用している謎も、これが戦闘訓練の一環という位置づけ故なのだろう、と捉えられる。
終盤でマームケステルが対魔獣の結界システムを備えていることが判明するのは先に書いた通りなのだが、この魔獣との戦いというのは実は『Lapis Re:LiGHTs』の世界において、常に人類を脅かしている危機なのである。このことについても、やはり序盤はあまり表には出てこないのだが、物語が進むに連れて段々と表面化している。9話では、ティアラが実家へと送還される中で魔獣に襲われた被害の残る街を見ている。彼女がマームケステルという閉じた籠のような街を離れることになり、その見る世界が否応なしに広がることと、この魔獣の被害を知るタイミングが一致しているというのは、なんとも示唆的である。
このような世界において魔女に期待される役割というのは、魔法を駆使して魔獣と率先して戦うことでもある。すなわち、マームケステルの魔法学院というのはというのは一種の軍学校めいた側面があると言える。平時では指導に当たっていた学院の教官たちが、最終話の有事においては老若問わずに作戦に駆り出されているのは、一見平和な世界の裏側を見せられたようでなかなかショッキングであった。
本作の情報開示が無知であったティアラの眼差しと呼応していることは先に述べた通りであるが、そうして進むに連れて見えてくるこの世界の現状というのは、なかなかにシビアなものであったわけである。もちろん、こうしたシビアさを認識していなかったのは他の生徒も同様であろう。ティアラたちと同じく最低ランクのラピスランク*3であったシュガーポケッツというグループのシャンペは、自身らのオルケストラの成否が街の命運を握っているという重圧に耐えられず、役目を放棄して思わず逃げ出そうとしている(11話)
ここで「できることをできる限りやるだけ」と説得され踏みとどまったシャンペは、最終回のオルケストラで『シャノワール』というポップソングを歌う。軽快な恋する乙女の歌詞の裏に、シャンペの決意が存在している。世界の危機とは無関係なハッピーなラブソングだが、そこにあるのは一種の切実さであり、シャンペたちは必死に歌を届けているのである。この作品はライブアクションにCGを用いているのだが、そんな中でも汗を流して歌い踊るシャンペたちを描いているのは、このシーンに血肉を通わせるための演出だろうか。
そしてシャンペたちが笑顔の裏側で戦っている同時刻に、魔獣の進行を食い止めるために人知れず兵士たちが戦っている。明るい曲調で「君が恋した私はシャノワール / その笑顔も視線もさらってく」と歌われるその裏側で、若い兵士が無惨にも踏み潰され、おそらく命を落としている。ここでのオルケストラ(音楽)は魔獣を食い止めるための切り札なのだが、しかし上滑りするような幸せな歌詞を聞いて私が否応なしに感じてしまうのは、音楽というものの、どうしようもない無力さである。
それでも音楽家たちが「やれることをできる範囲で」やろうとした場合、できることはポップソングを人々に届けることだけなのである。ここに、あの震災の状況で何かしらを行おうとして、音楽を鳴らしたミュージシャンたちの姿を思い出さないだろうか?


右:魔獣に踏み潰される若き兵士(12話)
ラピスリライツの魔獣というものは、成すすべのない災害であると同時に、音楽によって打ち倒されるものでもある。『Lapis Re:LiGHTs』において、オルケストラ(音楽)が対魔獣の切り札であるという設定は、音楽が直接的に災害に対して作用することができないという現実をベースにした上で、そこからフィクションとしてのハッピーエンドへの跳躍のため存在するかのように思える。
ところで、ノベルに書かれている魔獣の設定を見てみると「人のマイナス感情によって生まれる」ものであるらしい。これは、ラピスリライツというコンテンツが見据えている、音楽の働きが感じ取れる設定ではないかと思う。あくまでも、音楽というのは人の心を癒やす程度のものなのである。

「できることをできる範囲で」というスケール
「音楽の持つ力を描く」しかし「音楽は基本的に無力である」この絶妙に相反する音楽観によって出力されているのではないか、と感じる設定が一つある。それは、主人公のLiGHTsのチームというのは、アニメでは学園においてどうしようもない落ちこぼれであるという点である。つまり、LiGHTsというのは別にそれほど音楽によって強い影響力をもたず、寧ろ世の中からは認められない寄りの存在なのである。
「音楽って世の中を変えられるすごいものなんだ!」と、ピュアに信じているだけではなく「結局のところそんなに大したものじゃないじゃないか」と、冷めたところも感じさせるのがこのアニメの持ち味だと私は思っている。もっとも、これは私がそういう価値感だからそう感じているだけかもしれないが。
ところで、ティアラ(たち)の憧れている、ティアラの姉・エリザ率いるRAYというのは、立場的にはLiGHTsの対極にいるグループである。RAYは多大な支持の元で、更に「歌に魔法を乗せる」というエリザの能力によって魔獣の撃退も何度もこなしている伝説的グループであるという。学校を退学にまでなった落ちこぼれグループのLiGHTsにはできないことを、RAYは達成している。同じ「光」のモチーフのグループ名でも、ぼんやりとした明かりを思わせる「LiGHTs」と強烈な光線を思わせる「RAY」のニュアンスの違いというのは、このようなグループのあり方を反映した部分を思わせる。
もっとも、そんな人々から伝説的に扱われているRAYも、プライベートでは素行に問題*4があったりと、立派なだけの人々というわけではないらしい。元メンバーのクロエ曰く「ロゼッタさんたちの班(LiGHTs前身)は、エリザがいなかった頃の私達(RAY前身)にどことなく似ていた」とのことらしい(8話)結局エリザは多大な魔法の力を行使し続けたことで声を失ってしまうのだが、LiGHTs同様に無邪気に音楽を人々に届けていただけのはずのグループが、あまりにも強大な力を持っていたが故の悲劇、と言えるかもしれない。
ちなみに、この作品では珍しい、娯楽的用途の魔法の使い方は実はエリザが使用している。華麗に花を舞わせるその魔法は純粋に人々の心を癒やすためだけの魔法であり、そんな魔法の使い方をしていたエリザが大きな役割を背負うことになってしまったのは、やはり悲劇的であるように思える。

12話での最後のオルケストラにて、LiGHTsも魔獣を撃退する大切な役割を担っている。とはいえ、最後に現れた彼女らは最後の一押し*5をしただけにすぎないのだ。
しかし、みんなの力を借りるというティアラの言葉に、かつて一身に大きな役割を果たそうとしていたエリザは、ティアラのあり方を認めることになる。結局のところ、この世界の魔獣は根絶されたわけではない。しかしきっとよりより未来が来るだろう、ということを感じさせ、物語は幕引きとなる。目の前の問題をなんとか解決する、というこのあり方に、『Lapis Re:LiGHTs』の描く「できることのスケール感」が現れている。
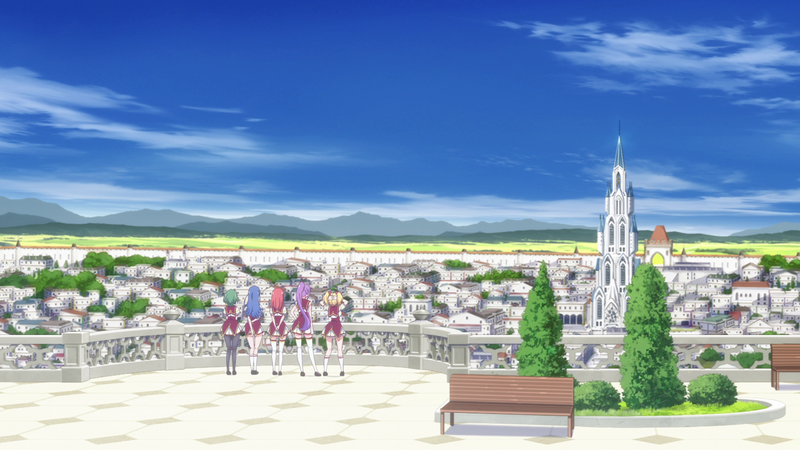
振り返ってみると、繰り返し登場する「できることをできる範囲で」という言葉*6は、非常にこの作品において象徴的な言葉だなと思う。何も大きなことを成さなくてもいい。ほんの少しの人の心を癒やすことができるというのは、とても大切で、かけがえのないことではないか。『Lapis Re:LiGHTs』の描く音楽の力というのは、そういうものだと、私は思うのである。
おわりに
『Lapis Re:LiGHTs』の主人公ユニットの名前をつけるシーンで、ティアラは街の明かりを見下ろしながら「いつか私も、こんな風に街を……人を照らす、光になれたらって!」と語りながら「LiGHTs」という名前をつける。街の明かりというのは人々の想いを集めた魔力によって照らされる、平和な営みの象徴である。本作のこのシーンに、私は停電や電力逼迫によって街の明かりが失われた出来事をどうしても想起してしまった。そうしたこともあって、直接的でないにしろ、2020年に放送されたこの作品は2011年の災害を踏まえた作品であると個人的には思っている。
そして同時に、この物語というのはオルケストラをやる存在、音楽を届けるもの”のみ”に光を当てているわけではない。『Lapis Re:LiGHTs』を見ていると、音楽をやる人々の周囲の人々、つまり街の人々や、オルケストラをやらない魔女の姿というのも頻繁に画面に映ることがわかるのである。そしてそこに注目しつつこのアニメを注意深く観察すると気がつくのだが、1話で彼女と馬車に乗っていた男性がフラレて、8話では酔い潰れていることがわかったりする。ちょっと一言二言話す背景の人にも、人一人の人生があるのである。
人を照らす光(LiGHTs)と、光(LiGHTs)に寄り添う人。そうした音楽と人との関係を、この作品は大切に描いてきた。

ところがいよいよ本作が放送されたという2020年というのは、COVID‑19という新たな危機によって人々が脅かされていた真っ只中であった。そしてご存知の通り、この危機によって人々と音楽という幸福な関係は、恐らく東日本大震災の時よりも遥かに、足元から揺さぶられてしまった。
ラピスリライツも音楽コンテンツとしてこの影響は少なからずあったであろうし、実際に2020年に予定されていたライブは見通しが立たないまま延期、結局2021年の9月に配信ライブとして開かれることになった。
この配信ライブそのものは非常によいもので、私もアニメ後に改めて「音楽というものはいいものだよな」ということを実感することができた。しかし、ついぞその後に、再びラピスリライツの音楽がステージで披露されることはなかった。アニメからファンになった私としても、リアルでステージを見ることは叶わなかったのである。
結局、コロナの危機から抜け出しつつあるかのような今を待たずに、ラピスリライツのプロジェクトは2022年にアプリゲームが一年もたずに終了してしまったことで、事実上終了となってしまったようだ。今となっては公式サイト*7も残っていないというのは、非常に物悲しいものがある。配信ライブのパンフレットの発送が遅れに遅れたことや、アプリゲームの配信も遅れに遅れたなどがあり、コロナに絡んでかそうでないかはわからないが、正直色々と順風満帆ではないのだろう、という感はあった。
日常が揺らいだひとつの災害以後に、改めて音楽というもののあり方を描く。それをやろうとしたアニメが『Lapis Re:LiGHTs』だったのだと私は思っている。そんな作品がまた新たな災害によって潰えてしまったということには、なんともやりきれなさや、哀しさを感じてしまう。
しかし、それでも、人々が無邪気に音楽の喜びを表現している時――それはちょうど2023年の今、ライブで歓声が上がったような瞬間にだ――私はふと、無力な音楽の持つ力を表現しようとしていたアニメが、ちょっと前にあったのだよな、ということを思い出すのである。


![【Amazon.co.jp限定】Everlasting Magic [初回限定盤] [CD + Blu-ray] (Amazon.co.jp限定特典 : メガジャケ〜初回限定盤絵柄〜 付) 【Amazon.co.jp限定】Everlasting Magic [初回限定盤] [CD + Blu-ray] (Amazon.co.jp限定特典 : メガジャケ〜初回限定盤絵柄〜 付)](https://m.media-amazon.com/images/I/51OgnK2UR+L._SL500_.jpg)
